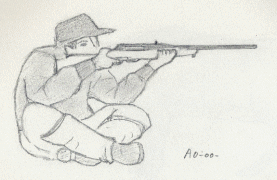| 私が三重県は菰野町田口新田の 故、舘剛氏が率いる猟隊へ加わる事と成ったのは 昭和49年度の 猟期でした 当時このグループは 親方の舘氏(通称タケさん)を始め 名の通った熟練者の集まりで タケさんの次男、美剛氏と共に猟場を走り回り 次々と起こる新たな体験に興奮が収まらなかった事を 昨日の事のように想いだします 今回はその頃の話をチョットばかり。 |
|
親方のタケさんに命じられ 待ち場へと立つ 短い時で 1時間 長くなると3〜4時間 寒風との我慢比べに成る。 瞬きも我慢して待つようにと 言い渡されることも有った、 それ位動くなとの意味だった のだろう。 その頃の服装では 現在の 化学素材を駆使した保温力 に優れた物など無く 汗に ぐっしょりと湿った綿の下着は 忽ち冷たくなり 体の芯から 冷え込んで来る。 抑えきれない震えの中にも 自らの持ち場を死守するとの 硬い意思に立ち尽くす・・。 |
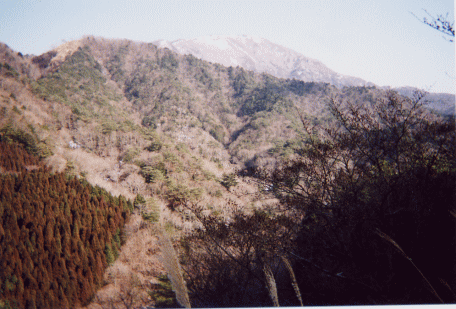 |